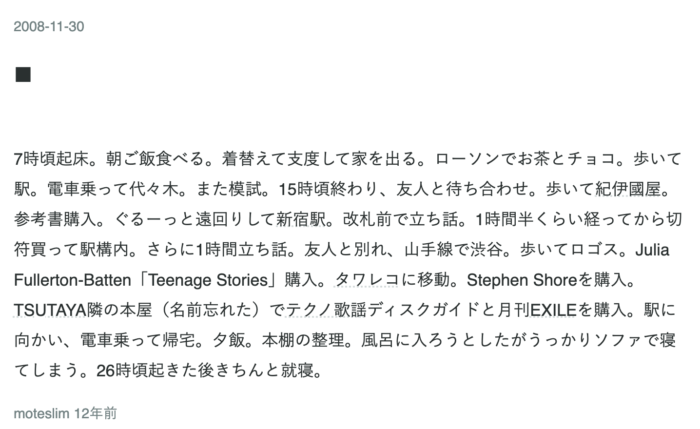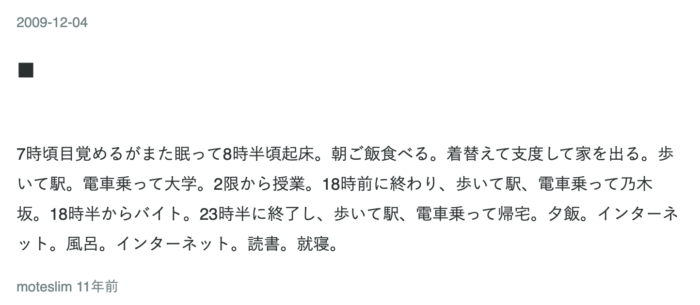
2020年12月3日
人はひとつの時代を、ドガーナの岬を通るように、つまり、かなりの速度で通り過ぎる。岬は近づいてきているのに、初めはその姿が見えない。次に、その場所まで来ると、それが突然目に入り、それはそのようにして建てられていたのであり、別な方法で建てられていたのではなかったと否応なく認めざるを得ない。だが、その時にはすでに、我々はその岬を回りきってしまっていて、それを後にして、未知の海を進んでいる。
ギィ・ドゥボール「われわれは夜に彷徨い歩こう、そしてすべてが火で焼き尽くされんことを」(『映画に反対して―ドゥボール映画作品全集〈上〉』)
2020年12月2日
高校生のときに読んだメンズノンノの美容ページで、とある男性スタイリストが「ニューヨークは乾燥しているので、ホテルに着いたらまずシャワーで熱湯を出して、部屋の湿度を上げるようにしています」と語っていたことを、10年以上経ったいまでも覚えている。というか、実践している。12月の北京で、1月のソウルで、2月の台南で。なかでもAirbnbで押さえた部屋は冷たく乾燥していることが多く、男性スタイリストの知恵は大いに役立った。
シャワーのハンドルを捻ると、ほどなくしてバスルームのミラーが曇り始める。数分経って部屋にぼんやりと湿気が移動したのを見届けて、お湯を止める。時間が経つと湿度の感触は消えてしまうが、こんなことをするのは最初に部屋に入ったときくらいで何度も繰り返すことはなく、だからなのかどこか儀式じみてもいた。
自宅で風呂場の換気扇を止めてシャワーを浴びながら、ひさびさにメンズノンノの記事のことを思い出していた。扉を開けると湯気が外へ広がる。換気扇をつける。湯気は吸い込まれる。外に漏れた湯気が、部屋の湿度を上げた。この部屋の窓はやたらに大きく、冬場に加湿器をつけると結露することも少なくなかった。それは好ましいことではなかったが、結露は嫌いではなかった。窓ガラスが曇る。視界が遮られる。指でなぞると結露は水滴となって垂れ下がり、窓ガラスは再び透明になる。もっとも、結露があらゆる面で部屋によくないことを知ってからは加湿器の扱いに注意を払うようになってしまったのだが。
冬は曇ったガラスの季節だ。かつて毎朝電車に乗って登校していたころ、乗車率200%に達する東西線の窓ガラスは人々の熱気でほのかに曇っていた。それは明らかに汚ない印象を与えていたが、冬の景色でもあった。雨や雪が降り、学校やタクシーの窓ガラスが曇る。曇ったガラスになにかを描いて遊ぶことをいつ辞めたのかは思い出せなかった。いま思えば、あれは密閉された空間の景色だったのだろう。あらゆる乗り物や建物が窓と扉を開け放っている2020年の冬から失われる景色。窓を開けると、結露はおさまる。風が通り抜け、窓は再び透明さを取り戻す。トランスペアレンシー。
ふたつ目は、ラジカルな透明性(Radical Transparency)です。わたしが議長を務める会議や、わたしが行ったインタビューなどは、このインタビューも含めて全て録音して、クリエイティブ・コモンズを使って公開しています。記録を見れば、わたしがどれだけ公共の利益のために活動をしているかを判断してもらうことができます。ただ公開するだけなのですが、こうした公開情報がセクターを超えたコラボレーションをもたらすことにもなります。文化の翻訳者のようなものです。
ホログラムで市民と対話!? 全世界が注目する台湾の”デジタル大臣”オードリー・タンが語るCOVID-19対策と新しいデモクラシーのかたち
台湾のデジタル大臣オードリー・タンが行政に導入するラジカルな透明性(Radical Transparency)はたしかに説得的だった。果たして日本で実現される日は来るだろうか。米サンフランシスコ発のD2C企業Everlaneも素材や原価、人件費を公開するラジカルな透明性によって若い世代を中心に支持を集めたことで知られている(今年に入って従業員解雇が問題となってはいるものの)。あるいは、現代中国では監視カメラが都市を覆いつくした結果犯罪率も下がり、通りに面した店舗でも閉店後にシャッターを下ろす必要がなくなりつつあると聞いたこともある。渋谷には透明な公共トイレがつくられたらしい。トランスペアレンシーの時代だ。
不透明な仕組みは非対称性を生み、ときに大きな暴力を引き起こす。透明性を実現することは、フェアネスを取り戻すことでもあるだろう。さまざまな通路が開け放たれ、窓は透き通っていく。髪を乾かしてからリビングに戻ろうとすると、風呂場からこぼれた湯気によってドアにはめ込まれたガラスの一部が少しだけ曇っていた。その不純さを懐かしむようにして、タオルで結露を拭き取った。
2020年12月1日
渋谷スクランブルスクエアから渋谷駅を通ってスクランブル交差点へ抜けると、昼の渋谷の風景が一気に目の中に入ってきて眩しく、眩しさから逃れるように交差点を渡って109に向かって進む。LUSHの前まで来るともう眩しくない。109のエントランスにはスクリーンが置かれていて、bibigoという韓国のメーカーから発売されている餃子のCMが流れていた。美味しそうに餃子を頬張る男性はパク・ソジュンというらしい。韓国の餃子のCMというのが妙に新鮮で、脳裏にパク・ソジュンの笑顔が焼きつく。
東急本店に向けて歩き出すと、ソウルを歩いているような気分に襲われる。109の冬のキャンペーンではNiziUが起用されていて、あちこちに大きなポスターが貼られていた。道沿いにはトッポギの店が看板を出していた。変化に変化を重ねて自分の知らない街になりかけている渋谷を見ながら、たとえばレイシストの人々はこうした変化をして日本が犯されていると思ったりするのだろうかと考える。それはなにか、自分の見知ったものが失われていく寂しさでもあるのだろうか。変わってしまうことをよしとしながらどこかで寂しさも感じている自分の気持ちは、何かをきっかけにして排外主義に変異しうるだろうか。数日前にNIKEが公開したCMは日本国内の差別問題に触れていて、ひどい反発を受けているらしかった。淀んだ川が目の前に流れている。川幅はさほど大きくないが、流れは速く、泳いで渡ることはできないだろう。橋も見当たらなかった。仕方なく座り込む。座ってる場合じゃないだろう、と遠くから声が聞こえてくる。立ち上がる。
東急本店の前を通るころにはすっかりソウルの気分が体の中まで染み込んでいて、あちこちにソウルの手がかりを見出そうとするのだった。カフェやパン屋、ラーメン屋。すべてを渋谷ではない場所にあるものと変換すると意外なほどにしっくりくる。何を見ても何かを思い出し、何を見ても何かを忘れ去る。空間に貼りついた記憶をせっせと剥がして、またべつの土地からもってきた記憶を無理やり貼りつける。松濤郵便局前の交差点を左折し、坂をのぼる。右手の建物にはBALENCIAGAのポスターがたくさん貼られていた。何かがどこかでオープンすることをそのポスターは告げていた。
自分にとってこの坂はとりわけソウルの風景を喚起した。ホンデの大通りから一本裏に入ったあたりの道や、アパレルショップが並ぶアックジョンの裏通り、あるいはまたべつのどこか。いくつもの街並みが明滅し、渋谷の風景に貼りつき、また剥がれていく。剥がれ落ちてしまわないように、急いでまたべつの何かを貼りつける。そんなことを繰り返すうちにユーロスペースの前まで来ていた。ここもどこかに似ているなと思いながら館内に吸い込まれていったが、自分がどこを思い出しているのかはまったくわからなかった。